精読の授業で魯迅の「薬」を読んでいる。息子の結核を治すために人血にひたした饅頭(マントウ)を買ってくる話だ。
これを読んでから、饅頭が食べられなくなってしまった。先生は「別に赤くもないし、大丈夫だろう」と言うんだけど、食堂に行って饅頭が並んでいるのを見てあの弾力とかを思い出すとどうにもダメだ。食いしんぼうで鋼鉄の胃袋をもつと自負していたのに、情けない。もしかすると、すっかり中国にも慣れてずぶとく生活しているようでも、やっぱり精神的に不安定な部分があるのかもしれない。
記憶がはっきりしないが、随筆で「すし」というのがあった。筆者は子供のころ少し病的で、ものを食べることができなかった。母親がこのままでは死んでしまうと心配し、ある日、目の前で「お前を生んだお母さんの手だよ」と言って手を洗い、1つ1つ材料を見せながらすしを握って食べさせてくれるという内容だったと思う。そのときは「世の中いろんな人がいるんだなあ」くらいにしか思っていなかったのだが、今はその「食べられない」という感覚がよくわかる。
「薬」は確か前にも日本語訳で読んでいるはずなのだが、そのときには別に何とも思わなかった。たぶん字面をなぞっていただけだったんだろう。でも中国に来てみて日々あの饅頭を食べ、その食感や生活の中に饅頭のある風景を経験してみると、ぜんぜん違う。こういう経験をするのも勉強のうちなのか、知らないほうがよかったのかはよくわからない。
 Copyright secured by Digiprove © 2020
Copyright secured by Digiprove © 2020 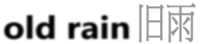


コメント