私はどうにもリスニングが弱い。思いあぐねて日華翻訳雑誌のゲストブックで相談してみたところ、听写をしなさいとアドバイスをいただいた。
それは、それまで私がやっていた何度もわからないところを巻き戻す听写とちょっと違っていたので、改めて听写をやり直してみようかと思った。先生は教材のテープだけを買って書き取るというのをやったそうだが、私はテキストを買わないのは不安でやっぱり買ってしまった。でも、听写が終わるまでは見ないことにして、しまってある。これはきちんと全部書き取るつもりで、遅々としたペースながら取り組んでいる。
このあいだ買った《听力篇》は、そういう正面からの听写では歯がたちそうにないというのは聞いてみてすぐにわかった。それで考え出したのがカンニング听写なのである。
リスニング力を高めるというのは、結局のところ音と頭の中の意味を結びつける作業だと思う。単なる聞き流しでも、その作業ができているならリスニングの練習になるのだろう。「○○語のシャワーを浴びる」という勉強法はこれだと思う。ただBGMとして聞いているなら、絶対に上達はしない。
でも聞き流しではついつい本当に聞き流してしまいやすいので、音と意味が結びついたのか、確認する作業を入れると強制力がある。漢字で書き取ることで確認作業とするのが听写だと思う。
逆に言えば、書き取るのは確認のためだけなのだ。もし単語を知らないとか、音が聞き分けられないとかの理由で音と頭の中の意味が結びつかないのであれば、書き取ることに意味はなくなる。答えを見て結びつけてやればいいのだ。
…というのがカンニング听写の発想だった。しかし、やってみるとこれはこれで問題があった。
このあいだTV番組で脳科学者の茂木健一郎が「思い出せないことを思い出そうと苦しんでいるときが、一番脳にとっていいトレーニングになる」と言っていた。あまりにもあっさりスクリプトを見るとだんだん後ろめたい気持ちになる。多少は書き取ったピンインと前後の意味とであれこれ推理したりして苦しむべきだろう。でも、どのくらい苦しんだら答えを見ていいのか。このへんの見極めが難しいのだ。
Marieさんがコメントで「完璧主義でなかなかうまく手抜きができない」と言っていたけど、その気持ち、よくわかるんだなあ…。
そういうことでくよくよするよりも、カンニングだろうと何だろうととにかく量をたくさんやれ! というのが最終的な結論なのだが。
 Copyright secured by Digiprove © 2020
Copyright secured by Digiprove © 2020 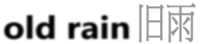


コメント